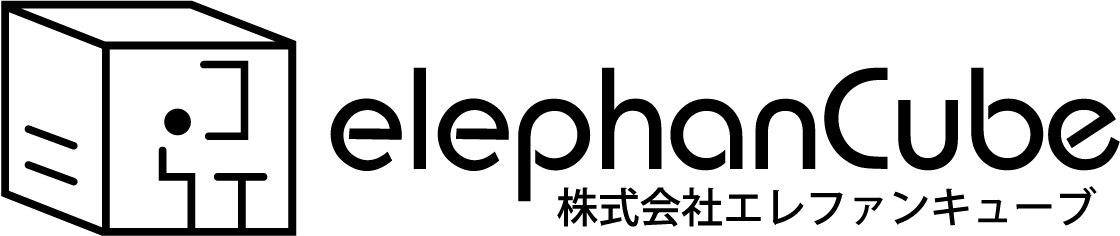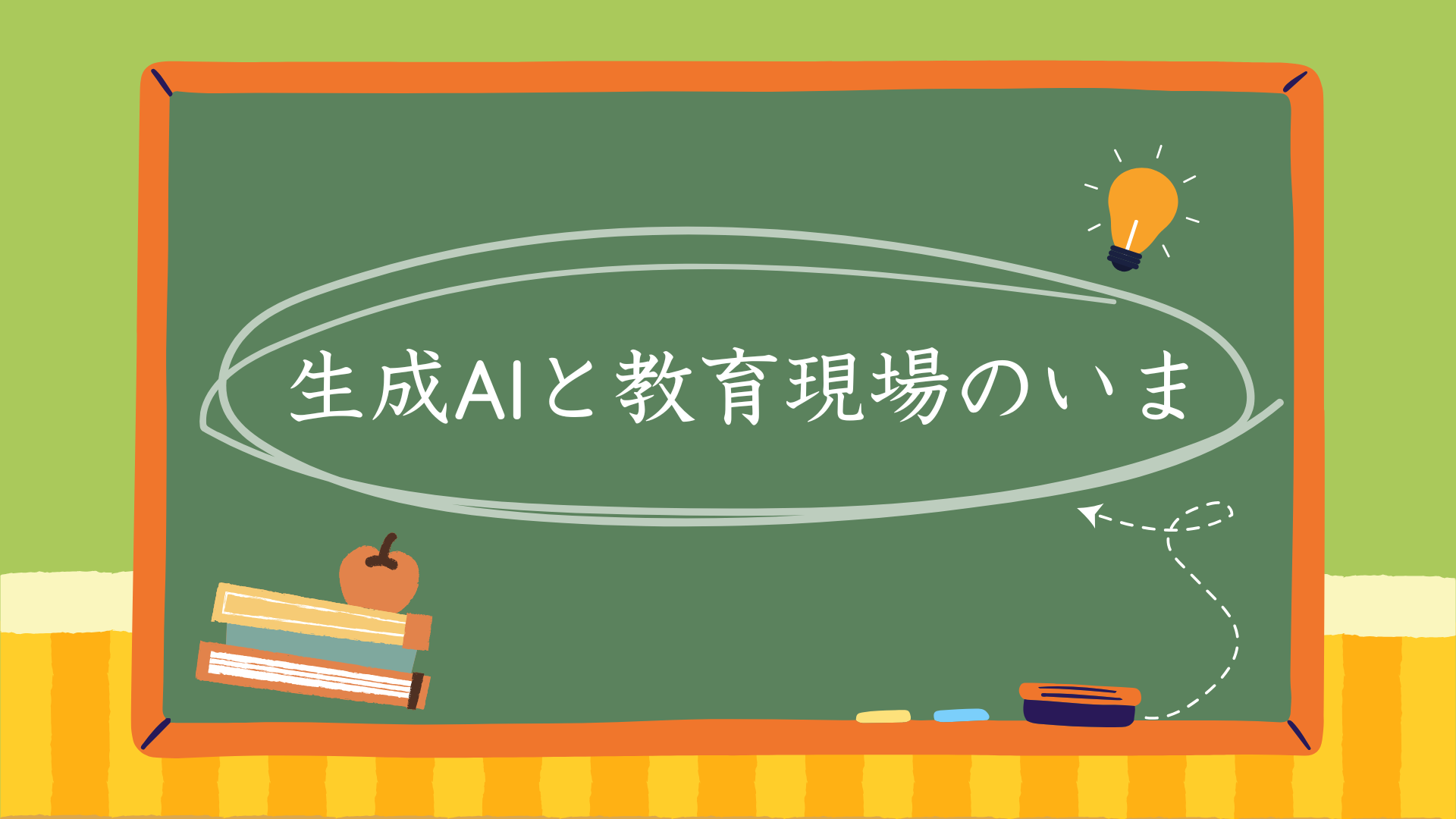ここ最近の生成AIの進化は目を見張るものがあり、私たちエレファンキューブの業務においても、なくてはならないものになりました。
さて今回は、学校教育現場における生成AI利活用についての記事です。
文部科学省の最新ガイドラインと、先進的な取り組みを進める自治体の事例をもとに、日本の学校教育における生成AI活用の「いま」を整理し、今後の教育コンテンツのあり方について考えてみます。
1. 文部科学省ガイドラインVer.2.0が示す「基本原則」
生成AIの急速な進化と現場での活用拡大を受け、文部科学省は2024年12月26日に「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver. 2.0)」を公表しました。これは、2023年7月の暫定的なガイドラインから一歩踏み込み、より具体的な活用場面と留意点を示したものです。
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/mext_02412.html
「人間中心」の原則と「情報活用能力」の強化
ガイドラインの根幹をなすのは、生成AIを「人間の能力を補助・拡張する有用な道具」と捉える「人間中心の原則」です。生成AIの出力はあくまで「参考の一つ」であり、最終的な判断と責任は人間(教職員や児童生徒)が持つべきであると明記されています。
また、生成AIを適切に使いこなすための前提として、学習指導要領に位置づけられている「情報活用能力」の育成が改めて強調されました。生成AIの仕組みや特性を理解し、その出力を鵜呑みにせず、批判的に検討する態度を育成することが、今後の教育において極めて重要となります。
| 主体 | 生成AI活用の基本的な考え方 |
|---|---|
| 児童生徒の学び | 学習指導要領に示す資質・能力の育成や、教育活動の目的を達成するために利活用する。出力は「参考」と認識し、批判的検討の態度を育成する。 |
| 教職員の役割 | 指導計画や学習環境の設定、丁寧な見取りと支援といった、学びの専門職としての役割は変わらず重要。AIリテラシーを身につけ、適切な活用を主導する。 |
| 情報活用能力 | 生成AIの特性(ハルシネーション、バイアス等)を理解し、情報モラルを含む情報活用能力の育成を充実させる。 |
教職員の「働き方改革」への貢献と留意点
ガイドラインでは、教職員の校務における生成AIの活用についても言及されており、授業準備、部活動、生徒指導等にかかわる業務の支援や、校務の効率化・質の向上を通じた「働き方改革」への貢献が期待されています。
ただし、利活用の際には、「原則、重要性の高い個人情報等をインプットしない」という厳格なルールが設けられています。個人情報保護法や著作権法を遵守し、安全かつ適切に利用することが求められます。
2. 【事例紹介】東京都「都立AI」に見る実践の最前線
ガイドラインの公表後、各自治体では具体的な導入が進んでいます。その中でも、東京都教育委員会は2025年5月より、全都立学校(256校、児童・生徒数約14万人)を対象に、独自の生成AIサービス「都立AI」の活用を開始しました。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/05/2025051209
この取り組みの大きな特徴は、安全性と利便性の両立にあります。都立AIは、入力したデータがAIの学習に利用されない環境を構築し、不適切なやり取りのフィルタリング機能を備えることで、児童生徒が安心して利用できる環境を整備しています。また、様々なプロンプト(生成AIへの指示文)のテンプレートを用意し、教職員と児童生徒が簡単に活用できるように工夫されています。
「生成AI研究校」での実証実験では、以下のようなテーマで生成AIが活用されました。
- 多角的な見解の調査: ロボットの利点と欠点について、生成AIを用いて様々な視点から見解を調べる。
- 生成AIの特性理解: 俳句や笑い話を作成させ、生成AIの得意分野と苦手分野を知る。
- 創造的な活動の支援: 学校紹介動画の作成にあたり、外部の人の知りたい情報を生成AIに案出しさせる。
これらの事例は、生成AIが単なる情報検索ツールではなく、思考を深めるための対話相手や、創造性を刺激するブレインストーミングのパートナーとして機能し始めていることを示しています。
3. 教育現場が直面する「次の課題」
生成AIの導入が進む一方で、教育現場は新たな課題にも直面しています。これらの課題を克服することが、生成AIを真に教育の力とするための鍵となります。
課題1: 教員間のリテラシー格差と研修の必要性
生成AIの活用度合いは、教員個人のデジタルリテラシーに大きく依存します。生成AIを積極的に活用し、教材研究や校務効率化に役立てる教員がいる一方で、利用に戸惑いを感じる教員も少なくありません。この**リテラシー格差**を埋めるため、教育委員会等による体系的かつ実践的な研修プログラムの整備が急務となっています。
課題2: 評価方法の再構築
児童生徒が生成AIを活用して作成したレポートや成果物を、どのように評価するのかという問題も重要です。単に最終成果物だけを評価するのではなく、生成AIをどのように活用したかというプロセスや、生成AIの出力を批判的に検討し、自分の考えを付け加えた思考力を重視した評価への転換が求められています。
課題3: デジタル教材との連携
生成AIは、既存のeラーニングやデジタル教材と連携することで、その効果を飛躍的に高める可能性があります。例えば、生成AIが個々の学習者の進捗や理解度に合わせて、デジタル教材内の最適なコンテンツをレコメンドしたり、教材の内容に基づいた個別指導の対話を提供したりすることが考えられます。デジタル教材制作の専門家として、この「AIとデジタル教材の統合」は、今後の教育コンテンツ開発における最重要テーマの一つです。
4. まとめ:生成AI時代における教育コンテンツの未来
2025年秋、日本の教育現場は、生成AIという強力なツールを手にし、大きな変革期を迎えています。文部科学省のガイドラインは、この変革を安全かつ適切に進めるための羅針盤となり、東京都の事例は、その実践的な可能性を示しています。
生成AIは、教師の負担を軽減し、児童生徒一人ひとりに最適化された学びを提供する可能性を秘めています。しかし、その力を最大限に引き出すためには、「人間中心」の原則を忘れず、情報活用能力の育成を土台とし、そして質の高いデジタル教材との有機的な連携が不可欠です。
私たちエレファンキューブは、長年にわたり培ってきたデジタル教材制作のノウハウと、最新の生成AI技術に関する知見を融合させ、教育現場のニーズに応える新しい教育コンテンツの開発に貢献してまいります。生成AI時代における教育コンテンツのあり方について、ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最終更新日: 2025-11-19