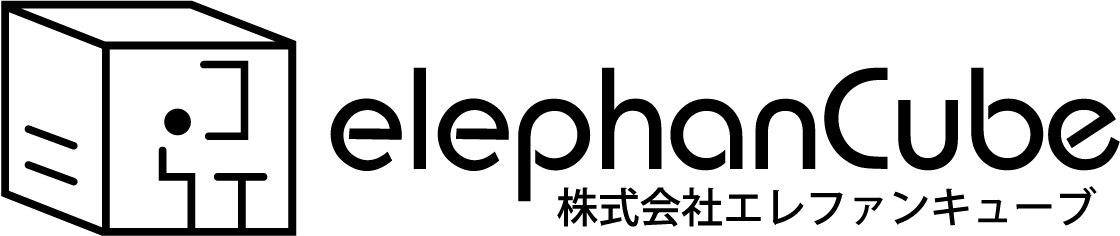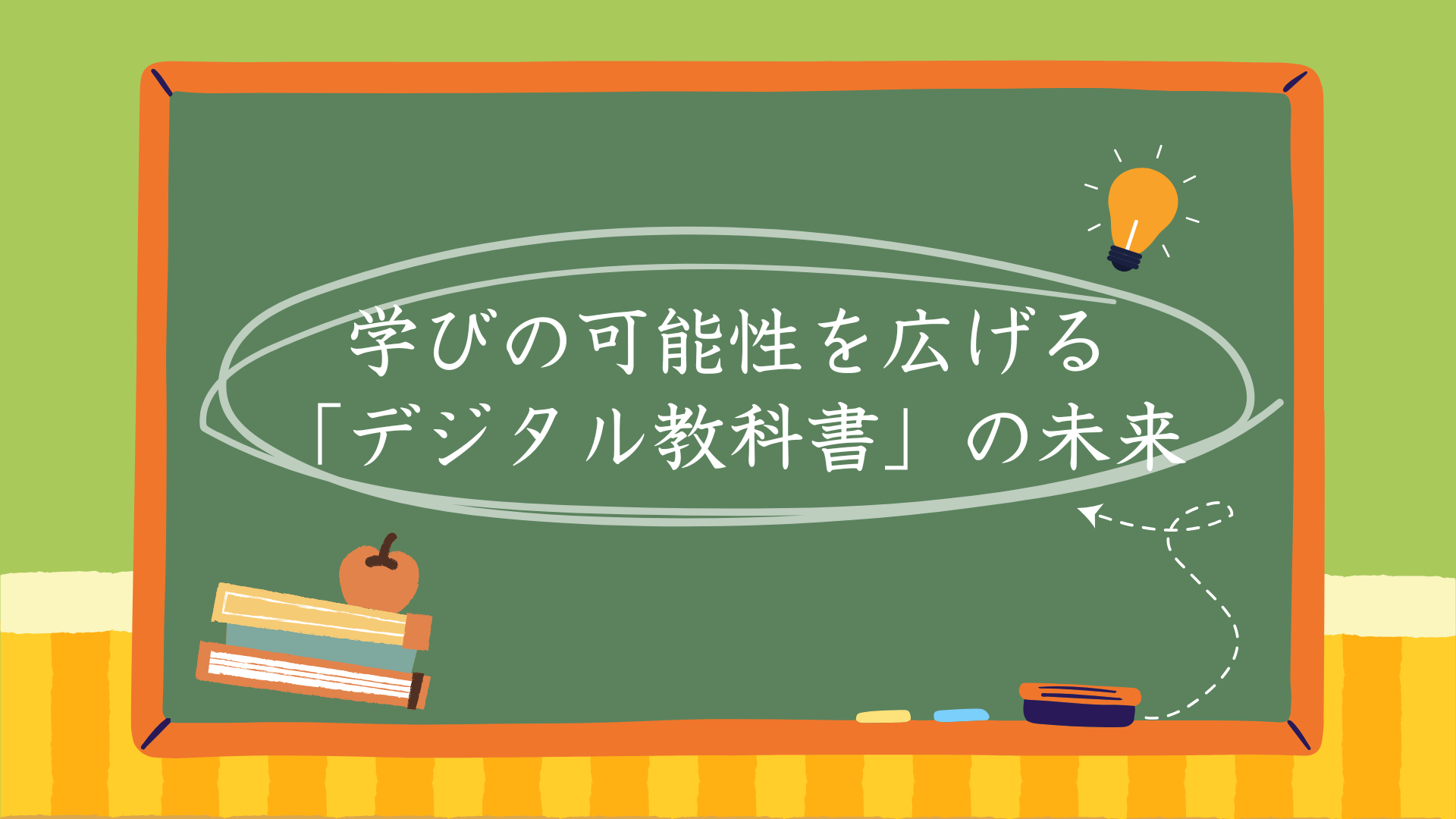2025年9月、文部科学省の審議会で重要な審議まとめが公表されました。これまで紙だけだった教科書に、デジタルという新たな選択肢を加える方向性が示されています。
この記事では、中央教育審議会初等中等教育分科会デジタル学習基盤特別委員会「デジタル教科書推進ワーキンググループ」による審議まとめ(令和7年9月24日)の内容を詳しく解説します。
本記事の元となったソースはこちらです。https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/100/toushin/mext_00012.html
なぜ今、教科書が変わるのか
私たちの生活は、スマートフォンやAIの登場で大きく変わりました。2010年頃から急速に広がったスマートフォンの利用率は、2023年には9割を超えています。生成AIの普及も目覚ましく、私たちの知的活動や日々の生活に大きな影響を与えています。
学校教育も例外ではありません。「GIGAスクール構想」により、児童生徒一人に一台の端末が整備され、高速通信ネットワークも99.4%の普通教室で利用可能になりました(令和7年3月時点)。
こうした環境の変化を受けて、学校で使う主な教材である「教科書」も、時代に合わせて進化する必要があると考えられるようになったのです。
デジタル教科書って何?どんな機能があるの?
現在のデジタル教科書は、紙の教科書の内容をそのままデジタル化したもので、様々な便利な機能が付いています。
主な機能
- 文字の拡大・縮小
- 背景や文字の色の変更
- 音声読み上げ
- ルビ(ふりがな)表示
- 書き込み・消去・保存
- リフロー(文章の折り返し表示)
これらの機能により、例えば視覚に困難がある子どもでも教科書が読みやすくなったり、日本語が苦手な子どもでも音声で確認しながら学習できたりします。
現場で見えてきた効果
令和6年度の大規模調査によると、デジタル教科書を「いつも使う」児童生徒は、そうでない児童生徒に比べて、授業の内容がよく分かっていると感じている割合が高く、主体的・対話的で深い学びを行っている割合も高いことが分かりました。
英語での活用事例
音声読み上げ機能により、ネイティブスピーカーの発音を何度も聞いて練習できるようになりました。再生速度も調整できるので、自分のペースで学習できます。教師からは「児童生徒が自信を持って前向きに言語活動に取り組むようになった」「発音やイントネーションへの意識が高まった」という声が寄せられています。
算数・数学での活用事例
シミュレーション機能を使うことで、図形を自由に動かしながら考えることができます。紙の教科書ではできない試行錯誤が可能になり、教師からは「デジタル教科書を使って一番大きく変わったのが授業展開」「実際に試行錯誤しながら図形やグラフを動かすことで、深い考えが形成されるようになった」という報告がされています。
また、書き込みや修正が容易なため、子どもは失敗を恐れずに何度も試行錯誤を繰り返すようになったという声も多く聞かれます。
国語での活用事例
マーカー機能や本文抜き出しツールを活用することで、自分の思考を視覚化しやすくなりました。紙の教科書では修正に手間がかかり書き込みを積極的に行いにくかったのが、デジタルでは訂正が容易なため、書き込みの量が格段に増えたという報告があります。
大きな転換:紙「だけ」から紙「も」デジタル「も」へ
今回の審議まとめで最も重要なのは、教科書の形態として、紙だけでなくデジタルも認めるという方向性が示されたことです。
これまでの制度
現在の制度では、「教科書」として認められているのは紙の図書だけです。デジタル教科書は「教科書代替教材」という位置づけで、あくまで紙の教科書に「代えて使用できる」特別な教材という扱いでした。
そのため、検定や採択、無償給与の対象は紙の教科書だけで、デジタル教科書は対象外でした。
審議まとめで示された方向性
今後は、紙とデジタルの両方を「教科書」として認め、学校や地域の実態に応じて選択できるようにすることが提案されています。
さらに興味深いのは、一部が紙、一部がデジタルという「ハイブリッド型」の教科書も認めるという方向性です。
例えば:
- 本文部分は紙に掲載し、発展的な内容はデジタル部分に掲載
- 英語の長文は紙に掲載し、音声やチャンツ等はデジタル部分に掲載
- 算数・数学で、計算や演習問題は紙に掲載し、図形のシミュレーションはデジタル部分に掲載
このように、紙とデジタルそれぞれの良さを生かした教科書作りが可能になります。
紙かデジタルか、ではなく「組み合わせ」
重要なのは、「紙かデジタルか」という二者択一ではないということです。審議まとめでは、紙の良さ、デジタルの良さ、そしてリアルな体験活動を適切に組み合わせてデザインすることが強調されています。
紙の良さ
- 一覧性や俯瞰性がある
- 書く作業によって記憶や理解が深まる
- 教科書を開いたまま、別の作業ができる
デジタルの良さ
- 音声や動画で理解を深められる
- 図形を動かしながら試行錯誤できる
- 自分のペースで繰り返し学習できる
- 書き込みや修正が簡単
- 重い教科書を持ち運ばなくてよい
デジタル教科書を使う場合でも、内容によっては印刷したものや紙のノートを活用しながら書いたり思考を深めたりする作業を重視することが求められます。
導入に向けた課題と対策
アカウント管理の負担
学校現場で最も大きな課題とされているのが、アカウント設定・管理の負担です。
これに対して、国や民間では改善の取り組みが進んでいます。令和6年度からは、登録用ファイルのフォーマットを統一し、一つのファイルでどのビューアでも登録できるようになりました。令和7年度からは、簡単な指定だけで複数ビューアのアカウント登録が自動的にできる無償サービスも提供されています。
健康への配慮
視力低下など健康影響を懸念する声もありますが、専門家の意見によると、授業では常に手元の教科書だけを見ているわけではなく、黒板や先生など遠くを見る状況もあることが通常です。
大切なのは、紙であってもデジタルであっても、長時間継続して近距離で注視することを避けることです。国では、健康に関する留意事項をガイドラインや通知で周知していますが、今後さらに徹底することが必要とされています。
通信環境の改善
デジタル教科書を快適に使うには、安定した通信環境が必要です。国では、GIGA スクール構想第2期として、端末の更新支援やネットワーク環境の改善に向けた取組を進めています。
いつから変わるの?
審議まとめでは、次期学習指導要領の実施に合わせて新たな形態の教科書が使用できるようにすることが望ましいとされています。
そのために、文部科学省、教科書発行者をはじめとした関係者が、必要な制度改正や関連する準備作業を着実かつ計画的に進めていくことが必要とされています。
教師の役割はますます重要に
デジタルを活用することは、授業時間の全てを端末の操作に費やすことを意味するのではありません。むしろ、紙の良さに加えてデジタルの良さも生かし、リアルの活動も適切に組み合わせて授業をデザインする教師の役割が極めて重要とされています。
そのため、国では以下の取り組みを充実させていくことが必要とされています:
- 効果的な活用方法の発信
- 様々な教科・学年の実践事例の創出
- 都道府県レベルなど広域での教員研修の充実
- 教員養成課程における取組の充実
まとめ:学びの可能性を広げる選択肢
今回の審議まとめは、教科書にデジタルという新たな選択肢を加えることで、児童生徒一人ひとりに合わせた「個別最適な学び」と、互いに学び合う「協働的な学び」の一体的な充実を目指す方向性を示しています。
大切なのは、デジタル化を目的にするのではなく、子どもたちの学びを充実させるためにどのような教科書が良いのかという視点です。紙とデジタル、それぞれの良さを生かしながら、学校や地域、子どもたちの実態に応じて最適な教材を選択できる環境の整備が提案されています。
これからの教育は、教科書「を」教えるのではなく、教科書「で」教えるという考え方に転換していく必要があります。多様な選択肢の中から、現場が主体的に判断し、創意工夫を発揮できる制度づくりが検討されています。
デジタル教材の制作会社として
私たちエレファンキューブは、デジタル教材の制作会社として、今回の審議まとめで示された方向性を大変心強く受け止めています。
これまでも、デジタル教科書や教材の制作に携わる中で、デジタルだからこそできる表現が子どもたちの学びを大きく変える瞬間に何度も立ち会ってきました。図形が動くことで「なるほど!」と目を輝かせる子どもたち、音声機能で自信を持って英語を発音できるようになった子どもたち、書き込みと消去を繰り返しながら自分なりの答えを見つけていく子どもたち――そうした姿が、私たちの原動力です。
今回、紙とデジタルを組み合わせた「ハイブリッド型」の教科書も含めて、多様な形態が認められる方向性が示されたことで、制作会社としての創意工夫の幅が大きく広がると感じています。
例えば:
- 動きで理解を深める:静止画では伝わりにくい事象を、アニメーションやシミュレーションで直感的に理解できるようにする
- 音で学びを豊かにする:言語学習だけでなく、音楽や理科の現象など、音声が本質的に重要な学習内容を効果的に提示する
- インタラクティブな学び:子どもたちが能動的に操作し、試行錯誤しながら学べるコンテンツを実現する
- 個別最適な表示:一人ひとりの見やすさや理解度に合わせて、表示方法や難易度を柔軟に調整できるようにする
ただし、私たちが常に心に留めているのは、技術のための技術ではなく、子どもたちの学びのためのデジタル表現であるということです。派手な演出や過剰な機能は、かえって学習の妨げになることもあります。
審議まとめでも強調されているように、デジタルは万能ではなく、紙の良さ、リアルな体験の重要性も変わりません。だからこそ、デジタルならではの強みを最大限に生かしつつ、紙やリアルな活動と自然に組み合わせられるような教材づくりを目指していきます。
また、教材を実際に使う教師の皆様の声を大切にし、授業での使いやすさ、準備の負担軽減にも配慮した設計を心がけていきます。
今後、制度改正に向けた具体的な検討が進む中で、私たちも教科書発行者の皆様、教育現場の皆様とともに、子どもたちの「学びの可能性を広げる」教材づくりに全力で取り組んでまいります。
デジタル教材の制作に関するご相談やお問い合わせは、ぜひエレファンキューブまでお気軽にお寄せください。
最終更新日: 2025-11-19