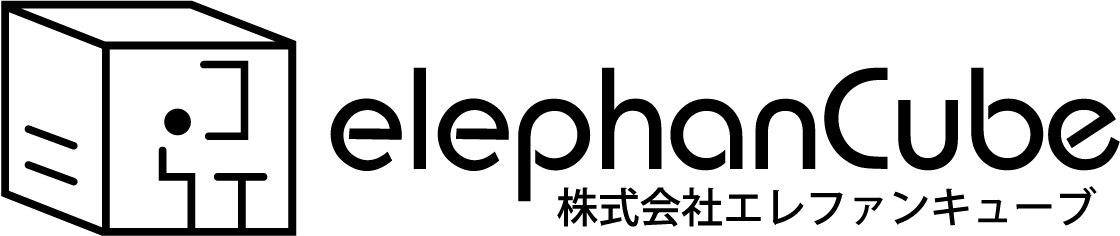近年、増加傾向にある企業のパワハラ問題に対して遂に国がメスを入れ、2020年6月に大企業を対象に改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が施行され、企業にはパワーハラスメントの防止措置が義務付けられました。そして、2022年4月より中小企業も義務化となりました。
今回は「パワハラ防止法」の内容を確認すると共に、企業に義務付けられたパワハラ防止措置、そしてハラスメント教育についてお伝えします。
<目次>
パワハラとは
パワハラとは「パワーハラスメント」の略語で、業務上での優位的立場を利用しながら、その範囲を超えた言動で、部下・後輩・同僚に対し執拗な嫌がらせ・いじめ行為を行って、相手に精神的・肉体的な不快感や苦痛を与えることを指します。
ただし、客観的に見て「業務上に必要な適正指導、業務指示などについては、職場におけるパワハラには該当しない」とされています。
厚生労働省「職場のパワーハラスメント防止のための指針」(ガイドライン)
増え続けるパワハラ相談
厚生労働省の調査によれば過去10年間、総合労働相談コーナーに寄せられた職場内での「嫌がらせ・いじめ」は、相談内容の中でもダントツに多く、またその件数は2倍以上に増えています。相談が寄せられたものは、ほんの一部であることが予想されるため、実際のパワハラ被害の件数は、これより多いと考えられます。
パワハラ防止法とは
近年、企業におけるパワハラ(虐め・嫌がらせ)問題は増える一方である傾向から、国は法律でパワハラを規定し、各企業に「パワハラ防止措置」を講じるよう義務づけました。
2019年5月に法律で「パワハラ防止法」が成立し、大企業は2020年6月から、中小企業は準備期間を置き2022年4月から施行されています。
法律で定められた「パワハラ防止法」
法令の中に記された「パワハラ防止法」は、昭和41年法律第132号において、「労働施策の総合的な推進、並びに労働者の雇用の安定、及び職業生活の充実等に関する法律」の中の第9章「職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等」で企業への義務化を講じています。
「第30条の2 雇用管理上の措置等」では
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して「解雇」その他不利益な取り扱いをしてはならない。
(注意:本文は読みやすくするために、句読点、「」を文章に加えています。)
「パワハラ防止法」の目的
国が「パワハラ防止法」を施行する理由は、これからの日本の課題にある少子高齢化による労働人口の減少が挙げられます。労働人口が減少する中でのパワハラ問題は、更に労働人口減少に繋がる要因とも言えるため、対策に乗り出したことが伺えます。
また、「パワハラ防止法」を施行する目的としては、
- 労働者の雇用の安定と職業生活の充実
- 労働生産性の向上の促進や日本経済や社会の発展
- 失業者のない「完全雇用」を目指した社会
などが挙げられます。
パワハラ防止法の罰則・違反の行使
企業がパワハラ防止法に違反した場合、今のところ罰則は設けられていませんが、場合によっては「勧告・指導」の対象となり、従わない場合は企業名が公表されるため、その後の経営に影響を与え兼ねません。
また、企業が職場内のパワハラ行為に気づいていながら放置した場合には、「安全配慮義務」の面で、民法上の不法行為責任(民法第709条、第715条)に問われる可能性があります。
まずは、管理職の方々のパワハラ認知度を確認してみましょう。
厚生労働省の「あかるい職場応援団」サイトで、管理職用の確認動画が用意されています。
企業が構ずべきパワハラ防止措置
「パワハラ防止措置」のポイントは4つです。
- 企業内で「パワハラ防止策」の具体的なルールを明確にした上で、その内容を雇用者全員(派遣社員・契約社員を含む)に周知し、社全体でパワハラ防止に努めること
- パワハラ相談や苦情に適切な対応が講じられるよう、必要な体制を整えておくこと(例えば、相談窓口の設置・相談を受ける担当者の研修・マニュアルの作成 など)
- パワハラ事案に係る事後処理をスピーディーに適切に行う
(相談者のケア・パワハラ行為者への処罰・必要であれば人事異動等)
- 1~3までの措置と合わせ
- 相談者とパワハラを行った者へのプライバシーの保護
- 他の社員にも当事者のプライバシー保護を通達
- パワハラ相談を理由とした不利益取扱いの禁止(再発・二重被害の防止)
1. の「雇用者への周知」の例としては、就業規則に盛り込んだり、研修や社員教育で「ハラスメント教育」を行うことなどが挙げられます。
中小企業内でのパワハラ6タイプ
パワハラの参考例として、厚生労働省がまとめたものに6種類があります。
- 身体的な攻撃・・・暴行・傷害
- 精神的な攻撃・・・脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言
- 人間関係からの切り離し・・・隔離・仲間外れ・無視
- 過大な要求・・・明らかに遂行が難しい業務の強制
- 過小な要求・・・仕事を与えない・能力や経験と見合わない仕事を振る
- 個への侵害・・・プライベートに過度に立ち入る
ハラスメント教育
パワハラを防ぐには、ハラスメントに関して正しく理解することが重要です。
無意識にパワハラ行為に及んでしまっていたり、人によって認識が異なっているケースもあるため、研修にて理解を促し、全体で共通認識を持つことによりパワハラの防止策に繋がります。
研修を実施するにあたって、eラーニングを活用することも1つの方法です。
eラーニング(教材)には、管理職向けや一般職向けなど、職位や立場に応じて作成されているものもありますが、それぞれ対象者全員が同じeラーニング(教材)を受講することで共通認識化を図ることができます。また、研修後に理解度テストを行うことで、理解度を確認することも可能です。
eラーニングで共通認識を持ったうえで、集合研修にて事例(実際に起こった問題など)を取りあげ、ディスカッションをしたり、演習を行うことで、問題がどこにあったのか、どういう対応をすればよかったのか、一人ひとりが主体的に考えられるようになります。
まとめ
これから労働人口が減る日本においては、安定した職場環境づくりがポイントであり、そのためにもパワハラが行われない職場を目指した取り組みが重要です。
企業でしっかりとパワハラ防止策を練ることで、雇用者は企業に対する安心感と信頼感を得ることができ、それによって生産性や業務効率の向上に繋がれば、企業にとってのメリットは大きいのではないでしょうか。
最終更新日: 2023-09-22